球体関節人形と女性(1)
なぜ球体関節人形作家に女性が多いのか?
創作人形としての球体関節人形(註1)について考えるとき、これまであまり正面切ってその理由が問われてこなかったのは、製作者の割合が、男性よりも女性が多いという事実である。またその人形の多くが女性身体であり、衣服を纏っている場合でも、衣服を外した時の裸体を見られることが想定されていて、裸体がかなり丹念に造り込まれているという特徴についてである。
これらのことはちょっと考えると当り前のように思えるがそうではない。たとえばヨーロッパのアンティークのビスク・ドールは顔、場合によっては手足など衣裳から露出した部分はビスクで大変よく造り込まれているが、衣裳の下の胴体部分はコンポジションやキッドなどで衣裳を着ることを前提として実用的に造られている。つまり衣裳を脱いだ状態で鑑賞しない前提となっている。オールビスクの人形もないわけではないが、割れやすいために大変小さな人形である場合が大半である。一方、日本の球体関節人形は裸体を見られることを前提として造られている。しばしば見られる腹の球体、四谷シモンの最近作に見られる胸のボールのような球体にはベルメールの影響が強く見てとれるが、それだけに留まらない、あからさまではない程度の、そして時にはかなり明確なテーマとしてのエロティシズムがそこでは意識されているように見える。
球体関節人形の創り手の多くは女性である。そしてヘテロセクシュアル(異性愛)の女性の欲望は少なくとも直接的には同性の裸体には向かわない筈である。では同性の裸体を精密に作ろうとする女性作家の欲望はどこから来るのだろうか。そしてどこに向かおうとしているのだろうか。そして最初に書いたように、そもそもなぜ球体関節人形作家に女性が多いのか?これらのことを考えるために、しばらく日本の球体関節人形の特徴を追いかけてみることにしよう。

左:創作人形専門誌『ドール・フォーラム・ジャパン』第40号 特集ー球体関節人形展ー(東京都現代美術館)表紙
表紙作品「無題(タンバリンを持つ少女」制作:天野可淡 「球体関節人形展」会場にて撮影
右:球体関節人形展 DOLLS OF INNOCENCE 図録表紙
球体関節人形作家をもっとも体系的にかつ大規模に扱った展覧会として、2004年に東京都現代美術館で開催された「球体関節人形展」が挙げられよう。それ故ここではこの代表的な展覧会の作家の性別を先ずは見てみることにしたい。
「球体関節人形展」にあわせて制作された図録の目次に挙げられている作家名は18名、これに足して著作権上の理由により図録には掲載されなかったが、多くの作品がまとめて出品され話題を呼んだ天野可淡をこれに加える(註2)。このうち、現代日本の人形作家ではないハンス・ベルメールと、人形ならぬ人間を球体関節人形に見立てて写真作品にした現代美術家のマリオ・Aを外す。また男女数人のユニットである「月光社」(註3)も便宜上外すことにする。こうして現代日本の人形作家のみに限定すると、女性10人、男性6人となる。これだけでも女性の方が人数的に優位であるが、男性の人形作家の場合、必ずしも球体関節人形のみを造っているわけではない作家たちが含まれている。たとえば片岡昌は「ひょっこりひょうたん島」の人形で知られるようにむしろ人形劇の人形作家として名声を確立した人物であるし、中村寝郎もよねやまりゅうも造型作品によって著名なプロフェッショナルな造型作家である。山本じんは球体関節人形においても著名であるが、画家、彫刻家としても知られ、特に銀筆画に独創的な作品を生み出している。山本の場合は自分が求める世界観がまずあり、球体関節人形もその美意識に適ったものであったと言えようか。一方、女性の作家たちは球体関節人形を作る前にマネキン制作会社に勤めていた土井典をのぞけば、概ねその制作は球体関節人形を中心に行なわれていると言える。
男性的な視線の欲望の対象化
もう一つ重要なのは、球体関節人形作家に女性が多いということもあってか、裸身の女性の人形が多いにもかかわらず、そこにはヘテロセクシュアル(異性愛)の男性の女性身体に対する視線もしくは視線の欲望が、少なくとも露骨には見られないという特徴があることである。そのもっとも代表的な具体例として、この球体関節人形による表現の在り方を最初に確立した四谷シモンの存在とその人形の在り方が挙げられよう。
日本の球体関節人形の祖というべき四谷シモンが、最初にその作品を個展の形で世に問うたのは、1973年の青木画廊での第1回個展「未来と過去のイヴ」である。彼はここで12点の等身大の女性像としての球体関節人形を出品した。それは女性の裸体の等身大の迫力ある人形であり、身につけているのはおおむねガーターストッキングと高いハイヒールのみである。その身体はふくらんだ胸やくびれた腰や張った尻という女性身体の特徴を充たしているが、いかつい顔や肩の造型や挑発的なまでに派手な化粧にもうひとつの特徴がある。
当時、四谷シモンは状況劇場で役者として女形をつとめていた。これらの人形の化粧した顔は、まさに女形としての四谷シモンの顔そのものであった。今年2014年に横浜美術館で開催された展覧会の図録『SIMON DOLL』にも「12体の女性像は、女形としてのシモンそのものであり、状況劇場時代の自画像とも言える」と指摘されている。

雑誌『芸術生活』1973年11月号「特集 人形愛」の表紙
表紙作品は四谷シモンの人形

1973年に青木画廊で開催された四谷シモン人形展のポスター
また四谷シモンはこの個展の前年に「10人の写真家による被写体 四谷シモン展」を紀伊國屋画廊で開催していた。これは篠山紀信、細江英公、沢渡朔ら、当代一流の写真家10人が四谷シモンを被写体として撮った展覧会であり、そこで四谷シモンは「被写体」としての魅力を遺憾なく発揮している。
近年まで絵画や彫刻においては男性が制作し女性がモデルとなるのが通常であり、写真においても男性が撮影し、女性が被写体となる傾向があり、プロフェッショナルな女性写真家にその逆の例もあるものの、2014年現在においてさえもまだ限定的であるといえる。そして、ベルメールの場合も自ら女性の人形を制作し、男性視点から女性の人形を被写体として写真に撮っていた(註4)。
ところが四谷シモンの場合は、その制作の出発点において、逆に当代一流の写真家たちの眼に晒される写真の被写体を経験していた。つまり彼は、球体関節人形作家として世に登場する寸前に、自らベルメールの球体関節人形写真の人形のポジション、対象としてのポジションに立っていたと言える。
またこの展覧会に彼は球体関節人形を一点だけ出品していたが、「状況劇場を退団後、人形作家としての実質的なデビューとなった」(註5)この展覧会において、彼が展示した等身大の球体関節人形は『ドイツの少年』というタイトルの少年の人形であった。彼はそれまでにも既に女性の球体関節人形を制作していたが、彼の実質的なデビュー作品としての球体関節人形の性別は男性であった。
彼が球体関節人形作家として世に広く刻印されることになるこれらの作品は全て彼自身をモデルとしており、彼はそこで作り手であると同時に被写体であった(註6)。
人形と男性のポジション
そしてこのことによって四谷シモンは、女性の球体関節人形を造る女性の人形作家と似たポジションに立っていたと言える。つまり自らが作り手であると同時に被写体であるというポジションである。自らが主体であると同時に対象であるというポジションである。これは四谷シモンが女性的であるということではない。なぜなら性別が女性であることと対象のポジションにあることは同じことではないからである。このことは西欧中心の世界観のなかで、非西欧の人間が男性であっても対象のポジションに置かれることを見れば容易に理解されよう。
四谷シモンの少年から大人に至る自画像の典型は少年像であり、男性像である。そのデビュー作の女性像は女形としての自画像である。彼が女性作家とそのポジションの在り方において似通ってくるのは、女性が同性である女性の裸体を制作する時に先ず置かれるポジション、作り手であるとともに被写体であるというそのポジションの在り方と,彼の人形製作におけるポジションが相似しているからである。
すなわち異性愛の男性の欲望が中心で、その欲望が正常であると長い間想定されてきた芸術において、それとは異なるポジションに立って作品制作をしたことが、四谷シモンの作品の重要な特徴であったと言えるし、これらの初期作品がその後の日本の球体関節人形の方向を決定付けたのではないだろうか。あるいは別の言い方をすれば、四谷シモンのような作家が初めにこれまでなかなか見られなかったタイプの女性裸体像を提示したからこそ、多くの女性たちがそれまで目にしてきた女性裸体像にはない特徴をそこに見出し、そこに意識的無意識的を問わず強いインスピレーションを得、そこから自分自身の作品作りに向っていったのではないか、と仮定することができるのである。
このことと関連して、最初に取り上げなかった2人の男性作家について言及しておきたい。まず、関節人形にとって重要かつ実績のある男性作家として吉田良が挙げられるが、彼の経歴は写真から出発しており、天野可淡のパートナーとして、そして彼女の作品を撮った写真家として、また人形教室ピグマリオンで多くの球体関節人形作家を育てた師として、そうした多彩な球体関節人形への貢献によってその名声を獲得しているとも言える。また月光社は才能ある人形作家つじとしゆきを中心とする人形製作ユニットであるが、服装制作などに女性を入れ、あえて男性のみの制作とはしていない。つまり球体関節人形の代表的な男性の人形作家は、意識的であるかそうでないかを問わず、ヘテロセクシャルの男性による女性への欲望をストレートに人形化するような形での仕事をしていないという共通点があるのである。
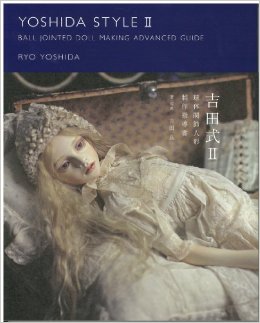
『吉田式II 球体関節人形 制作指導書』(2014)の表紙
つまり創作人形としての球体関節人形のユニークな特徴は、その多くが女性の裸体という外見を持ちながらも、ヘテロセクシュアルの男性の欲望を反映した女性ヌードの在り方とは別の表現になっているということなのである。
このことはこの連載でも紹介した女性作家・土井典、時代的には四谷シモンと同時期にベルメール作品に模した球体関節人形作品を造り、四谷シモンと並んで、球体関節人形制作の第一世代(註7)に属すると言える土井の作品にも繋がる要素である。なぜなら彼女の人形はこの「ヘテロセクシュアルの男性による女性への欲望」そのものを批判的に、あるいは逆向きに捉えることによって己の作品のテーマとしているからである。
日本の球体関節人形のポジション
上記のことを考えあわせると第二世代の球体関節人形作家に女性が多いのは、ただその人形が女性にとって魅力的であっただけではなく、造り手としての彼女たちの琴線に触れる魅力がそこにあったからではないかと考えることができる。
すなわちそこには、女性が作品を造る上での根本的な矛盾を解決する道筋が、言語化も意識化もはっきりされないままではあるが、見え隠れしていたのではないだろうか。
それらのテーマをあえて言語化するならば次のようなものになるだろう。
① 視線の対象として「見られる」から「見せる」へと移行すること
② 視線の対象の側から「見る」ものを「見返す」こと
③ 「見られるもの」の側から、「見るもの」「見られるもの」という構図の外に、
即ち、その構図そのものを「見る」位置に立つこと
四谷シモンの場合は、まずこの①と②が初期の作品において示されていたと言える。「女形」としての彼は、舞台に立ち、あるいは写真の被写体として、ただ受動的に「見られる」のではなく、自らを「見せる」「見させる」ことを自覚的に行なった。また「見せる」ことは、挑発的に見る者を見返すことに繋がった。つまり前者は受動的な対象としての状況はそのままにそれを無自覚な様態から自覚的な様態に変えるものであり、後者は「見るものー見られるもの」という構図はそのままに、「見られるもの」が、受動形から能動形へ自覚的に移行することになる。しかし「見るものー見られるもの」の両者の位置そのものが逆転するわけではない。それは彼の望むところではないからである。彼の自画像である彼の人形作品にはそうした態度とその視線の構造が反映していたと言える。そしてそれは女性の表現者が、女性という対象としてのポジションを維持しながら、自らの欲望を自覚的に描き出す「方法論」の一つのモデルとなったのではないだろうか。
一方、③はその「見るものー見られるもの」という構図そのものを括弧に入れ、その外に立つことであり、土井典の作品はこの①②以外に、部分的に③に関わっていると言える。
「人形」が二項的な関係に留まるものであるならば、この③の位置に立つことは、人形ではなくなることである。
「人形」ではなく何になるかと言えば、「人形」を素材に用いたコンセプチュアルな現代アートに近づいていくと言える。その方向に見出されるのがハンス・ベルメールの人形写真作品であり、20世紀後半の女性アーティスト、たとえばシンディ・シャーマンによる、自分自身や人形を用いた写真作品に見出されるような「視線」や「眼差し」(註8)の構造それ自体をテーマとした作品に繋がっていくのである。
土井典の作品はその意味で人形と現代アートの境目にあったと言える。
(次号につづく)
