1960-70年代の日本の女性アーティストの状況
さて、今回は、日本の球体関節人形と女性人形作家の関係を見る前に、1960-70年代に女性アーティストの置かれていた状況について、先日起こったろくでなし子氏の事件と絡めながら、見ておくことにしよう。
ろくでなし子とガラパゴス日本
2014年7月14日、芸術家・ろくでなし子氏が、自らの女性器を3Dプリンタ用データとして、活動資金を寄付した男性らにダウンロードさせた件で「わいせつ物頒布等の罪」で逮捕され、「表現の自由」を巡ってさまざまな論争や署名運動などが起こったことは記憶に新しい。かくして彼女はチャタレー事件、サド・悪徳の栄え事件、四畳半襖の下張り事件、愛のコリーダ事件などにならび、ラディカルな表現者として後世に名を残すことになった。
「捜査関係者は『取り調べ中にも何度も直截的な表現で自説を唱えていた。この3文字がこれだけ記載された供述調書は初めて。わいせつ犯というより思想犯だ』と苦笑」(産経新聞)したと言うが、この3文字を女性が唱えることは、男性にとっての「表現の自由」の問題とは思想的にいささか異なるものであったはずである。ちなみに彼女自身は問題の3文字言葉を繰り返し唱える理由について「女性器は女にとっては生理・セックス・妊娠・出産と、自分の肉体の一部としてあまりにも身近な物です。それが『わいせつ』という言葉によって、女性の持ち物であるにも関わらず、どこか遠い存在になっている。これはおかしいのではないかというのが、私の根底にはあります。」(ハフィントンポスト)と語っている。
「どこか遠い存在」とはどういうことだろうか。それはただ単に表現としてタブー視されているから「遠い存在」になっているということではない。彼女がいたるところで三文字言葉を繰り返し唱えるということは、タブーを犯すことではなく、むしろ逆に女性器やそれにまつわる言葉をタブー視することそのものへの根本的な批判なのである。
またそこには二つのテーマがあったのではないか。一つは「女性」というテーマ、一つは「当事者性」というテーマである。つまり、女性でありこの性器を「持つ」当事者であるわたしにとって女性器はわいせつではない、だから女性器はわいせつではない、という主張がそこではこめられているのである。そんなことは当り前のことではないかとも思えるが、ここで語られているのは具体的に自分の身体は自分の「もの」であるということと同時に、フェミニズムでいうところの家父長制社会において、女性が他者であり、女性の性器も女性自身のものではない、という既に50年以上前にフェミニズムがもたらした「発見」が背後にあるのである。つまりここで語られている「女性性器」を誰が所有するかという問題は極めて具体的であると同時に思想的な問題なのである。しかし、何故そういうことになるのだろうか。
かのボーヴォワールは『第二の性』(1954)のなかで「男は主体であり、絶対者である。つまり、女は他者なのだ」と述べている。そして当時の精神分析の知見を参照しながら、更にこうも述べていた。
少女は完全な客体になるように、自分を<他者>とみなすように仕向けられている。女の子が自分を男の子と比較するかどうかの問題は二の次である。重要なのは、意識しようとしまいと、ペニスがないことは女の子にとって性としての自分を自覚する妨げになっていることだ(ボーヴォワール『第二の性』)
つまり女性は「去勢」によって「ペニスがない」自分を発見し、ペニス羨望に陥る。それが女性の運命なのだというわけである。
しかしこれは本当に「運命」なのだろうか、と思考を巡らすだけではなく、その運命に対する果敢なる「挑戦」を試みたのが、1960年代後半に始まるアメリカのラディカル・フェミニズムであったといえよう。そしてこのラディカル・フェミニズムが牽引したのが、ろくでなし子氏が述べているような「わたしの身体はわたしのもの」だから「わたしの女性器はわたしのもの」という考え方なのである。
歴史的には、これは、1969年、自分自身の身体についての情報をあまりにも持っていないことをお互いの話し合いのなかから知った女性たちが、手作りで女性のからだの本を作っていった「ボストン女の健康の本コレクティヴ」において Our Bodies Ourselves というスローガンによって唱えられ、実践された主張である。女性の生殖器は男性のペニスのように見えやすいものではなく、また男性のペニスの補完物としてのヴァギナに限定されるものでもないので、それらをあらためて自ら知り、自らのものとして取戻していこうという草の根的な運動にそれは始まっていた。これは奇しくも、男性は「持つ」もの、女性は「ある」もの、という考え方に対して、あるいは男性が所用し、女性が所有される、という通念に対して、女性が「持つ」こと、自らを所有する権利を取戻そうとする運動でもあった。
同時代のフランスにおいては、精神分析の知見をいったん受け入れた上で、理論的にそれと格闘していこうとする傾向が勝っていたが、アメリカの場合は、現実変革の可能性を信じて、ポジティヴに突き進む傾向があったようである。それ故、自分の身体を取戻すために、自分の性器を見ること、知ること、語ること、描くこと、等々の具体的な行動が試みられたのである。そしてそれは同時代の現代美術にもすぐさま反映された。ジュディ・シカゴの『ディナー・パーティ』に代表されるようなフェミニスト・アートの試みはこうした背景から生まれたのである。


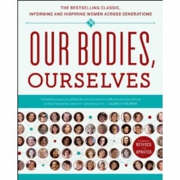
ろくでなし子のプロフィールによれば「現在は北原みのり主宰のラブピースクラブに勤務しながら漫画とデコまん創作活動を続けて」いるという。その北原は、70年代のウーマン・リブやフェミニズム・アートに強い影響を受けており、ろくでなし子の一件について次のように述べている。
ろくでなし子さんの「おまんこは手足と同じ!」という「主張」は、決して斬新なものではありません。正直に言えば私にとっては、「マンネリ」とでもいうような退屈なものでした。私自身が1997年に「まんこって言えるようになろうよ」みたいなことを言ってお店をはじめた女です。ジュディ・シカゴの『ディナーパーティ』の作品を全面にちりばめた上野千鶴子姐本に衝撃を受けた10代を過ごし、70年代のウーマンリブをオタクのように追いかけ、20年近くアダルトショップを経営している女からしてみれば、2010年代のなし子さんの「マンコをタブーにするな!」という主張は、今更? というようなもの。
もちろん、私がそう思っていることについては、なし子さんにも伝えたこともあります。「なし子さんが言ってることは、70年代から女たちが言ってきたことだよ」と。確か、おひるご飯を食べている時だったと思うんですが、私の言い方にトゲがあったんでしょうね、なし子さんはムッとして「私は知らない」って、言い切りました。で、こう仰ったんですよね。「私が知らないってことは、伝わるべき人に伝わってないってことなんじゃないですか」って。
なるほどね、って私ぐうの音も出なかったよ。フェミニズムの歴史なんかどうでもよくて、今ここに生きてる女に言葉届いてなかったら意味ねーよ、って全くその通りだから。そうだよね、いったい70年代から何が変わったんだろう? 80年代から、女の性の事情は、何が変わったんだろう? そんなことを、なし子さんの活動から私は、常に考えさせられてきました。
(北原みのり「ろくでなし子さんの逮捕に思うこと)
長い引用になったが、北原はここで、ろくでなし子がやっていること、またその主張それ自体は、既に40年以上前に存在していたことをあらためて確認している。
そしてその一方、ろくでなし子の「伝わるべき人に伝わっていない」という主張の前に、これらの主張がまだこの国では十分に伝わっていない、次世代に伝えられていないことも認めざるを得ないのである。ここには二つの問題がありそうだ。一つには日本ではまだフェミニズムへの偏見や拒絶反応が一部に根強くあり、フェミニズムを20世紀の重要な思想として、また21世紀に必要な一般常識として受け入れていく知的な土壌が広く形成されていないという事情があるということ、また、日本においてフェミニズムは、欧米から輸入された「女性学」が長らく牽引していたために、草の根的な運動やそこから発生する地道な思考が十分に育っていなかったということである。それは「ヴァギナ」という外来語では語られても「まんこ」という日常的な日本語はいまだにタブー視されていたこととも繋がっていよう。ろくでなし子氏の主張はこうした日本の事情を背景としていまだ十分にその意義を持っているのである。
前者の問題については、インターネットの急速な普及もあって、ようやく女性問題についての日本のガラパゴス的現状が見えやすくなってきたようである。今回のろくでなし子問題に対する対応の変化もそうした事情が後押ししているように見える。
フェミニスト・アートと女性性器の関係
ちなみに、女性性器を現代美術のテーマとしたアーティストの名を挙げるとしたら、北原みのりも述べてるように、ジュディ・シカゴの名が、そして作品としては『ディナー・パーティ』が筆頭にあげられるだろう。
これは彼女が1970年代に制作を開始し、1979年にサンフランシスコ美術館で展示されたフェミニスト・アートの代表的な作品であり、「39人の歴史上の偉大な女性の生涯を説明する刺繍で覆われた、三角形のテーブルの上に置かれた39枚のディナー皿を中心とするインスタレーションであり、外陰部の形のバリエーションで女性の歴史を描く」(参考資料3)というものである。この丸い皿に描かれた美しい色彩の模様が女性性器を象ったものであり、女性器を抽象的に象ったそれらの皿がそのディナーパーティのテーブルに並べられているという設定である。日本では、上野千鶴子の『女あそび』(1988)にこのジュディ・シカゴの作品が表紙に使われたことで、はじめてこのフェミニスト・アートの存在を知った人も多かったようである。では、日本にはフェミニスト・アートと呼べるものはほとんど育たなかったのだろうか。ところがどうもそうではないのである。その奇妙に「転倒」した事情について次に考えてみよう。

日本における女性アーティストの困難
戦前までの日本において、女性が画家になるにはいまだ大変な道のりがあったことは事実である。まず彼女たちを入れてくれる学校がなかった。東京美術学校(現・東京芸術大学)をはじめとしてほとんどの美術学校は女性を排除していた。例外は女子美術学校(現・女子美術大学)であったが、戦後、制度は変わってもなお人びとの意識は容易に変わるものではなかった。
あらためて見返してみて、ヨーロッパでは既に第二次世界大戦前から、シュルレアリスムに見られるように女性による性的な表現の過激な探究が見られるのだが、日本ではそうした表現がほとんど見当らなかったということだ。つまり日本にはレオノール・フィ二のような女性アーティストはいなかったということである。そもそも男性中心に展開されていた日本のシュルレアリスム自体に性的な要素が極めて薄いことは既に指摘されてきたことではある。
1960-70年代の日本でも、まだ女性アーティストの活躍にはいろいろな困難があったようで、そうしたあからさまに性的な作品はほとんど見当らない。現代美術において批評は重要な要素であるが、この時期盛んであった批評の分野にも女性はいなかった。例外として挙げるべきは日向あき子だが、まさに彼女は例外中の例外だったのである。
人形作家・土井典もそのような時代背景のなかで澁澤龍彦の周辺で活躍をはじめ、種村季弘や寺山修司らに評価されてその活動の枠を広げていった。彼女が、澁澤龍彦の注文によって1968年に作った「貞操帯」や陰毛をつけたマネキンやベルメールの人形を模した裸体の人形などは、日本国内で作られた作品としては当時十分にラディカルな作品であったと言えよう。
フルクサスと女性アーティスト
しかしそれを「日本における女性アーティスト」ではなく、「日本出身の女性アーティスト」の活躍と書き換えるならば実は事情はいささか異なっていたようである。
先述の女性性器と女性アーティストによる表現の問題を考える時に、有名な作品としてすぐ思い浮かぶのはジュディ・シカゴの『ディナー・パーティ』であろうが、しかし日本人の女性アーティストということになれば、久保田成子の『ヴァギナ・ペインティング』をまず挙げておかなければならないだろう。

これは実際にヴァギナを用いて絵を描いたのではなく、下着から赤い絵具を塗った絵筆を垂らして抽象画を描いたものである。写真を見ていただければ一目瞭然なので、参考写真をここに掲載するが、これは1965年ニューヨークで行なわれたものである。
現在写真として記録に残っているこの作品は、1965年当時、フルクサスの活動の一貫で行なわれたイヴェントであり、当時は仲間うちでも不評であったという。由本みどりによればこの作品は「フルクサスの仲間やその知人たちに衝撃を与えた。赤い形象はいわずもがな月経血や出産を覆わせたし、実際に女性器を使って描いているという誤解もあった」という。しかしともかくもそれは当時確かに行なわれたのであり、現在ではフェミニスト・アートの先駆的作品として国際的に高く評価されているのである。
また同年には小野洋子がやはりニューヨークで『カット・ピース』というパフォーマンスを行なっている。小野洋子は幼い頃から父の仕事の関係でアメリカと日本を往復しており、1952年に女性ではじめて学習院大学の哲学科に入学するも、父の転勤に伴いアメリカのサラ・ローレンス大学に編入、1955年に現代音楽の作曲家・一柳慧と結婚し、1960年前後から前衛芸術集団フルクサスと活動をともにするようになった。ビデオとして記録に残っているこの作品もフェミニスト・アートの先駆的アートとして現在よく知られているものである。自らの身体を舞台上において、その服を切らせるという衝撃的なパフォーマンスは一歩間違えば単にスキャンダラスなものとして消費されてしまいそうな危険を抱えている。この作品は実は前年の1964年に日本で行なわれていたが、まさにこの年に小野は2年間アーティストとして活躍した日本を去っている。
当時、日本の現代美術は、海外との交流が盛んになり始めていた時期であった。50年代後半からのフランスのアンフォルメル関係の画家たちの来日、また「ジョン・ケージ・ショック」と呼ばれることになる1962年のジョン・ケージの来日など海外からのアーティストの来日が増えていた一方、1950年代後半から海外に新境地を求める日本のアーティストも増え始めていた。
そしてそこで特徴的だったのは、女性のアーティストが割合として多かったことである。桂ユキ子を先駆者として、ざっと挙げるだけでも、草間彌生(1957年)、芥川沙織(1959年)、斉藤陽子(1953年)、塩見允枝子(1964年)、久保田成子(1964年)らがアメリカに向かった。
不可視の日本の女性アーティスト
彼女たちは何故アメリカに向かったのか。そこには当時、彼女たちの作品だけではなく、彼女たちの存在そのものが日本で受け入れられにくかったという事情が後押ししていたようである。小野洋子(オノ・ヨーコ)の場合も、1962年から1964年まで日本に帰国し、草月会館などを中心に前衛芸術のアーティストとして活躍するものの、日本での活動に空しさを覚えて再びアメリカへと旅立っていった。それは何故だったのだろう。以下の記述にその理由の一端が見える。
オノがアメリカに戻っていったほかの理由には、男性だらけの前衛界で紅一点的存在であった彼女が、しばしば不当な嘲笑や野次の対象にされたということがある。批評家たちはオノの「やることなすことすべてに対して小舅的な態度をとりつづけた」ほか、彼女の私生活までをも問題にした。
(由本みどり「フルクサスと日本人女性芸術家たち」)
また先述の久保田成子も「日本では女性のアーティストが認められるチャンスはないと思い」ニューヨークに旅立ったと証言している。
当時、女性たちが感じた日本社会に対するこの違和感はどこから来たのだろうか。幼い頃から日本とアメリカを往復し、後にアメリカ国籍となる小野洋子(オノ・ヨーコ)は例外的だとしても、日本で育った女性たちも戦後の、建前としては男女平等の教育を受け、その観念を受け入れていたにもかかわらず、実際の日本社会はその観念にまったく追いついてはいなかったのではないだろうか。こうした女性にとって困難な日本特有の環境から旅立ってきた故にか、当時の彼女たちの作品は「性差」に敏感なものが多く、アメリカでも1970年代初頭から始まったとされるフェミニスト・アートの先駆的存在として小野洋子、久保田成子、草間彌生らは、ニキ・ド・サンファール等と並んで高く評価されることになった。
とりわけ草間は早くからアメリカで目覚ましい活躍をしていたが、ここでは人形と女性というテーマとの関係で草間が当時マネキンを用いて作った作品を挙げておくことにしよう。草間は男根を模したソフトスカルプチュアを早くから製作しているが、「ファリック・ガール」というタイトルのこの作品においてもマネキンに多くのファルス状の物体が付けたられている。精神科医の斉藤環が『戦闘美少女の精神分析』でこの語を用いる30年あまり前に作られていた作品ということでも興味深いのではないだろうか。
ちなみに、草間にせよ、小野や久保田にせよ、こうした初期の作品や活動を知ろうとすると、英語の資料に頼らざるを得ない。海外での評価と日本での評価の落差は、女性の作家の方が男性の作家よりも大きいように見える。この点においても日本のガラパゴス的価値観はいまだ存続しているようである。(つづく)
